ここ最近、【ネオ終活】なるものがトレンドになっているらしいのです。20代の若者が終活を行っている(気にかけている)そうです。コロナ禍を経験し、突然亡くなる事は年齢に関係ないという状況が数年続いた背景からと言われています。
葬儀関連・相続問題・ラストメッセージなど、彼らの終活の心構えを拝聴していると、感心することばかり。死を考えたからこそ、今を充実させようという気合もみられ、強く前向きな気持ちがうかがえました。年齢を重ねると、自身の体や記憶の不調であったり、目の当たりにする介護懸念などのマイナスイメージばかりが先行し、自分が今どうしたいのかすら考えられなくなってしまいます。
終活は、身の回りの整理・もしもの時の事務手続き・相続を考える事だけではありません。比較的時間や体力もあり、生きていくための知恵もついている今。若者たちを見習って、今を充実させること・やり残したことが無いように行動する事も終活の一つです。前向きに取り組んでいきましょう。 終活は元気なうちに少しずつ





















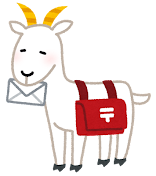


.png)









.png)







